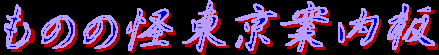浅草寺子院妙音院(明王院)
あさじがはら
●浅茅原の一つ家 −血を吸う石−
西に傾いた真っ赤な夕日は、みるみる草の間に落ちていった。
夕闇がしだいに濃くなる。
「よわったな」
旅の男はつぶやいて、辺りを見回した。
ここは名にしおう武蔵国浅茅が原。秋のことで、萩、ススキが身の丈よりも高く生い茂って、日が暮れて後は道もわからない。
がっしりとした体つきの、鬚の濃いその男は、狩衣姿で腰に大ぶりの太刀を帯びていた。陸奥から所用でいそいで上る途中、武蔵野にさしかかった。
道中、人から「日暮れてお通りになるのは無理ですよ」と止められたのだが、怖いものなしの力自慢から、強いて旅を続けたのである。
「だが、こう暗くては」
途方にくれた男の目に、草の間にチラとまたたく灯の色が映った。
「お、家がある」
救われたように、男は歩き出した。
草葺きの粗末な一つ家の戸を、男はこぶしで叩いた。
「旅のものだ。一夜の宿を頼みたい」
長いこと待たせた後、ようやく戸が開いた。
相手を一目見たとき、男は背筋に寒いものが走るのを覚えた。
ぼうぼうと乱れて顔にかかる白い髪、その奥からのぞく双の眼は、暗い二つの孔を見るようであった。
「宿を借りたいが」
男の声が、のどに絡まった。
相変わらず口はきかないが、老婆は身振りで、入れと促した。
踏み固められた土間の奥には、それでも筵を敷き、炉が切ってある。
チロチロと燃える榾火の向こうに、若い女の姿を認めたとき、男は心なしかホッとした。
男は火のそばへ寄り、手をかざした。陽が落ちれば早くも肌寒い晩秋の候である。衣類はしっとりと露にぬれていた。
ようやく暖まると、男は腰の餌袋をひらいた。中の糒(ほしい)を食べようとすると、
「汁粥おひとつどうぞ」
やさしい声とともに、娘が椀を差し出した。
「おお、これはありがたい」
あたたかい粥を男はむさぼり食った。
「ところで、あの瓢(ふくべ)の中身は酒かの」
壁に掛けられた瓢を指して、男は聞いた。
女はおかしそうに口に手を当てた。
「はい、母様の寝酒で」
「一口、わけてもらえまえか」
女は母親をふり返ってみた。
炉の火に小枝を折っては差し加えていた老婆は、黙って頷いた。
娘は身軽に断って、瓢を取り降ろした。
椀につがれた酒は、プンと妙な匂いがした。
が、元来酒好きの男はかまわず呷った。喉ごしに熱いものが下りていく。
「ううむ、どうもたまらぬ。もう一杯もらおうか。礼はする」
片隅に置いた荷物へ、男は目を走らせた。それは、衣類や手回りの品で大きくふくらんでいる。
瓢を取り上げて、娘は再び男の椀を満たした。
うつむいた横顔は、ようやく14、5歳というところか。
身につけている衣類は襤褸に等しいが、色白の整った顔立ちである。
「そなたたち、親子二人の暮らしか?」
椀に口を付けながら男は聞いた。
「はい。父はとうに失せました」
「もとから、ここにか?」
「はい」
「寂しくはないか?」
「慣れておりますから」
「なぜ、婿を迎えぬ」
娘の表情にふと愁いが浮かんだ。が、酔いが回っていた男は気が付かなかった。
「そなたほどの器量なら、男が放っておくまい」
「貧しい私どものもとへ来てくれる男など、ありませぬ」
「隠すな。毎夜のように夜這うものがあろう」
男の目が舐めるように、娘のからだを這い回った。
うつむいたまま、娘は空になった男の椀を、三度満たした。
どこへ行ったものか、老婆の姿が見えない。
男はこれ幸いと、手を伸ばして娘の手首を捕らえた。
むすめはなよなよとして、抗わない。かえって「こちらへ」と、奥へ導いた。
帳代わりの莚で仕切った一角に、枕と衾の用意があった。
旅の疲れか、酒のたたりか、石の枕に頭を置とすやいなや、男は雷鳴のようないびきをかきだした。
足音もたてず、娘は床をはなれていった。
やがて、女二人はひそひそと囁き交わした。
「眠ったかえ?」
「ええ。…でも…」
「また、そう悲しげな顔を見せる。そなたは、あの夜のことを忘れたのかえ?」
「ああ、もうあのことは……」
「わたしは忘れようと努めても、忘れられることではない。
あのときの無念、腸が煮えくりかえるようであった」
「でも、あのときの男と、今宵の旅のお人とは別人……」
「なんの。同じ『男』という獣よ。
今宵の男も始めのうちこそ殊勝らしく振る舞っておったが、
酒が入ればたちまち好色の牙を剥き出したではないか」
それから老婆は優しく声をあらためた。
「そなたは案じることはない。そなたに罪はない。
仏罰はみな、この母が身に引き受ける。さぁ、しばらく外へ」
娘を促して戸外へ出し、老婆は旅人の寝所に赴いた。
足音を忍ばせて、枕元へ近づいた。
三年前のあの夜の光景が、今も老婆の脳裏にありありと残る。
あのときの心の内を、何に喩えることができよう。
三年前──
道に行き暮れた旅の男を、老婆は気の毒に思い、宿を貸した。
残り物の粥も食わせてやり、炉の傍らに寝かせた。
ところが深夜、娘の悲鳴に目覚めてみると、男が娘の上に乗りかかっているではないか。
「何をする!」
あわてて引き下ろそうとしたが、女の力で動かばこそ。
男は歯をむき出しに笑いながら、からだの動きをやめようとしなかった。
老婆はもう無我夢中で、土間の草苅鎌をつかむやいなや、男の顔といわず体といわず斬りつけた。
血まみれになって、男は絶息した。
まだ少女といっていい12歳の娘は、無残に傷を負っていた。
貧しい暮らしの中でも、掌中の珠といつくしんできた独り子である。
行きずりの旅の男につぼみの花を散らされた口惜しさは、老婆の胸に余った。
男の死骸は身ぐるみ剥いで、裏の池へ投げ捨てた。
束の間、旅人から奪った金品で、母子二人の貧しい生活は潤った。
娘に美しい麻の小袖を整えることもできた。
次に現れた旅人も、老婆はためらわずに殺した。
そしてまた次も……。
浅茅原の一つ家に入って無事に出てきた男はなかった。
老婆は工夫して、旅人に石の枕をさせ、その真上に重い石を縄で吊った。
縄を切れば落ちた石が旅人の頭を砕く。
そして―― 今宵もまた、その仕掛けを用いた。
男の断末魔の悲鳴が響き、悶え苦しむ声が僅かな間続いた。
老婆は手探りで男の着物を剥いだ。
男の体はまだ生暖かく、時折、手足がピクリと動く。
あたり一面、血の匂いが漂う。
が、老婆はたじろぎもせず、もくもくと作業を進めた。
やがて、裸に剥いた男の体を引きずって、家の裏手へ出ると、力一杯にそれを池に落とし込んだ。
冷ややかな秋の月が中空高く昇って、血まみれの老婆を照らした。
戸口にたたずんでいた娘は思わず袖で顔を覆った。
それは、まごうことなき鬼女の姿であった……。
数日後のこと、旅人が戸を叩いたとき、それを開けたのは娘だった。
母親は寝酒を求めに里へ出ていた。
「日が暮れて難儀しております。宿をお貸し下さらぬか」
娘と同じ年頃の水干に括り袴のその稚児は、女のように優しい声で乞うた。
見るからに疲れ切った様子であった。
「なりませぬ」
とっさに娘は首を振った。
「なぜ?」
驚いたように少年は目をみはった。娘は口ごもった。
さすがに、母親の悪行をうちつけには言い出しにくい。
「お聞きなされませ」
娘は口ずさんだ。
日は暮れて 野には臥すとも宿借るな
あさくさ寺の 一つ家のうち
「──こういう歌を、誰か教え申しませんでしたか」
浅茅原の一つ家で行われている惨劇に、土地の人も薄々感づいていた。
噂話は娘の耳にも入っていた。
「さて、聞き及んでおりませぬが」
訝しそうに少年は涼しい顔で、じっと娘を見つめた。
人を疑うことを知らない、あどけない表情である。
娘は思わず顔を赤らめた。
「とにかく、ここはあなたのような方のお宿りあそばすところではございません。
早々お立ち退きなさるのがよろしゅうござりましょう」
「と申してもこの暗さでは」
少年がためらっているとき、ひたひたと野面に音がして、母が帰ってきた。
―― もう、どうすることもできない。
少年は請じ入れられ、例によって粥をふるまわれた。
揺れる榾火の向こうに浮かぶ少年の面差しに、娘は見とれた。
絵にあるような美しい稚児。生まれて初めて娘は恋の感情を味わった。
娘に見つめられて、恥じらうように顔を伏せた少年も、やがて自分の方からも思いを込めた視線を娘に送るようになった。
「こちらでお寝みなされませ」
娘は手を取って寝所へ導いた。
どちらからともなく、二人は抱き合った。少年の腕の中で娘は涙を流した。
「なぜ、泣かれます?」
問いかける少年の唇に、娘は指を押し当てた。
「静かに。母に聞かれてはなりませぬ。
ここは歌の如く恐ろしい家。
この枕には、数多の旅人の血が浸みこんでおります。
はやくお逃げなされませ」
娘の言葉は偽りとはみえなかった。心を残しながらも少年は一つ家を逃れ出た。
少しの寝酒にうたた寝していた老婆が、むっくりと身を起こした。
旅人は寝入ったらしく、あたりはひっそりと静まっている。
娘が今日の客人に心を動かした様子を、母親は知らないでもなかった。
旅人の幼さ、美しさは、これまでに殺したどの男とも違うものであった。
けれども、老婆にはもう人らしい情けは残っていなかった。
いま、炉の火に照らされた老婆のそそけ立つ髪、削げた顔、不気味な光を宿すその眼は、すでに鬼女そのものであった。
旅人の寝所へ忍び寄ると、灯りをかかげてその寝姿を見た。
白い衣を頭から被き、下げ髪の端が枕上に打ちやられている。それを見定めると、老婆は手にした刃物を振り上げ、大石を吊った縄を一気に断ち切った!
この世のものとも思われない断末魔の叫びが響き渡った!
そして、衣の下から転がり出たのは、何といとしい娘の体…!
母親は声も出なかった。あわてて取りすがったが、大石に頭を打ち砕かれた娘の、生きながらえられるわけもなかった。踏み潰した石榴のような娘の顔に、自分の顔をすりつけて、母親は号泣した。
「愚かものめ、愚かものめ」
娘があの美しい稚児の身代わりに立ったのだと悟り、母親は泣く泣く娘を罵った。
しかしまた、初めての恋に殉じた心根を思いやり、
「不憫やのう、いとしやのう」
と、夜一夜を泣き尽くし、やがて娘の亡骸を抱き上げると、そのまま家を出た。
裏の池の畔に立ち、今一度、娘をひしと抱きしめ、
老婆はそのまま池に身を投げたのだった――。