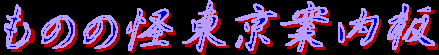
|
麹町・常仙寺/牛込御門内番町
●番町皿屋敷
番町皿屋敷の舞台となった青山主膳の邸は、もと天樹院の住んでいた御殿跡を
拝領したもので、牛込御門内番町にありました。 番町の名はこの地名からとったものなんですね。 また、青山主膳ではなく、青山播磨とする話もありますが、この人は摂津尼ヶ崎の領主で、 実は無関係なのです。 いやはや迷惑な話もあったもので…。
|
| 陽のよく当たる座敷で、お菊は片付けものをしていた。 主家の旗本・青山主膳の邸では、昨夜来客があり、そのときに用いた皿小鉢の類を、お菊は丹念に箱へしまっていた。 どれも客用の大切な器なので、お菊は念には念を入れてよく拭い、ひとつひとつあらためた。 ほっと息をついて、お菊は手を休め手の甲で汗を拭った。 5月に入り、雨が続いていたが、今日は珍しく晴れ上がって日差しも強い。 が、お菊が汗ばんでいたのはそのせいばかりではなかった。 お菊は今年十六。 艶やかに結い上げた島田髷に矢絣の単衣、黒繻子の帯の腰元姿がよく似合う、 美しい中にあどけなさの残る乙女であった。 大ぶりの錦手の鉢を箱におさめると、お菊はそれを胸に抱えて納戸へと、席を立った。 しばらくして戻ってきたお菊は、はっと廊下で足をとめた。 さっきまで自分のいた所に、主の青山主膳が座っていた。 お菊を認めると、頬をゆがめて、奇妙な笑いを浮かべた。 お菊はすぐ膝をついたが、胸の動機が早くなるのを止めることが出来なかった。 この正月、青山家に奉公に上がった最初の日から、主が自分に関心を抱いているのを 感じていた。 主膳は三十少し前の齢ごろで、むろん奥様を迎えている。 奥様は懐妊中で、この5月には出産の予定だった。 朋輩の話では、主膳はとくに道楽者というわけではなく、外で遊んでくることもないし、 家内の風儀もきちんとしているという。側女もおいていなかった。 小心で謹直な男であったのだろう。 ところが、お菊が腰元として勤めはじめると、主膳は妙なそぶりを示すようになった。 はじめは「奉公は辛くないか」と優しい言葉をかけるくらいだったのが、ことさら呼んで足腰をもませるとか、暗い部屋で抱きすくめるなどする。 武家では奥向きと表のべつがやかましい。 奥に働く女たちは、すべて奥様の監督下にあるのが建て前になっている。 「お菊を、殿様が勝手にお召し使いになっては困ります」 奥様は夫に抗議した。 むろん、お菊に傾いている夫の心中は察している。 平素は奥様の言いなりになる主膳だが、このときは聞えぬふりで答えなかった。 奥様はおもしろくなかった。ただでさえ懐妊中で、気が立っている。 お菊に冷たく当たるようになったのも、当然の成り行きであった。 お菊は当惑した。 主の態度も困ったものだが、奥様に憎まれるのはなお恐ろしい。 ふつうの奉公人なら、勤めづらいとみれば、暇をとることもできようが、お菊にはそれができぬ事情があった。 お菊の兄は向坂甚内という、四谷大木戸に住む侠客だったが、罪を犯して御仕置きを受け、 妹であるお菊は『一生奴』として青山家へ下げ渡されたのである。 四谷の兄のもとにいたころ、お菊は近所に住む幼馴染みの辰三郎に恋心を抱いていた。 ――いつかは、辰さんのおかみさんに… そんな夢を描いていたのも、にわかの境遇の変化で、微塵に打ち砕かれてしまった。 しかし、お菊はそれでもまだ辰三郎を忘れかね、主人の意に従う気には、どうしてもなれなかった。 主膳はお菊をあきらめられないらしく、ある日、お菊は女中頭のおさわに呼ばれ、主人の意向を伝えられた。 おさわはむかし、主膳の乳母だったという五十がらみの権高な女である。 「殿様は、たいそうそなたがお気に召され、『側女としてとり立ててつかわす』と まで仰せなのですよ。そもそも一生奴のそなたのこと、そこまでなさらずとも、 生かすも殺すもお心のままなのに、もともと真面目一方のお方なのです。 こんな有り難い思し召しに背くようなことがあれば、そなた、罰が当たりますよ」 おさわにまくし立てられ、お菊はただうつむくばかりであった。 「でも奥様の機嫌を損じましょう」 「なに、その点も案ずることはない。これだけのお旗本で、一人や二人、お側女の ないお家はありません。だいたいこちらの奥様はご悋気が過ぎます」 だが、どう説かれてもお菊は首をたてに振らなかった。年若くおしとやかに見えるが、侠客の妹だけあって、芯が強かった。 おさわもしまいにはさじを投げ、これこれと主に報告した。 主膳は額に青筋を立てながらも黙って聞いていたが、この日から、深くお菊を憎むようになった。 さて、お菊が座敷へ戻って主膳の姿をみとめ、顔色を変えると、その様子をじっと見つめていた主は妙にかすれた声音でこう聞いた。 「精出してよう勤めておるの。大儀じゃ。どの器も、きちんとそろっておるか」 「は、はい」 お菊は指をついた。 「よくあらためましたが、みなそろっております」 「それ、そこにある中国渡来の絵皿は、拝領の品で青山家の家宝じゃ。他の皿小鉢 の一枚二枚は惜しゅうないが、この絵皿ばかりはかけがえがない。存じておるか」 「はい、おさわ様からよく伺っておりますゆえ、とりわけ気をつけております」 「では、わしの目の前で箱に納めい。わしがこの手で、あちらへ片づけよう」 「恐れ入ります」 お菊は主膳の前に膝をつき、絵皿を一枚ずつ、よく拭っては鬱金木綿に包んでいった。 主膳はそうしたお菊の姿にじっと目をつけている。 緊張から、お菊の指先はややもすればふるえた。 一枚、二枚と皿を重ねていったお菊は、最後の皿をとり上げて、さっと蒼ざめた。 ――そんなはずはない。 周囲を見回したが、すべて器はしまわれた後で、そこにはもう何も見当たらない。 「いかがいたした」 主膳の陰気な声が、頭上から降ってくる。 「はい、いいえ」 お菊は狼狽して、今しまった皿を一枚ずつ取り出してみた。どう数えても、十枚あるはずの皿が九枚しかない。 「なにをしておる」 「あの、お皿が…」 「なに、皿が」 お菊はもう一度数えなおしてみた。そしてまた一度…。 「もしや、お台所方に残っているかもしれません。尋ねてまいります」 とどろく胸をおさえて、台所のものに尋ねてみたが、 「十枚、確かに数えてお返し申しました」 と、みな口をそろえて答える。 戻ってきたお菊の顔色は死人のようだった。家宝の皿を失ってはただではすまないことは、よくわかっていた。 くずれるように座りこむお菊を、冷ややかな微笑とともに、主膳はながめやった。 「皿は、ないか」 「……はい」 「ない、ではすまぬぞ」 折りも折り、廊下を奥様が通りかかった。 座敷の中で、何か様子あり気な夫とお菊に目をとめ、眉をひそめた。 主膳がおさわを使って、お菊に側女奉公を奨めた件は、奥様の耳にも入っていた。 お菊を憎いと思う心は、以前にもまさっていた。 夫の前にうつむいて震えているお菊の、細く白いうなじが奥様の目を射た。 二人がよからぬことをしている現場にぶつかったかのように、奥様の血は逆流した。 「なにをしておられます」 奥様は鋭く詰問した。 「菊が当家の重宝を扱っておる。慣れぬことゆえそそうのないよう申し聞かせたの じゃが、どうやら、皿が一枚、紛失いたした」 「そういうことでございましたか」 奥様は尻目にお菊を見た。 「日頃、ご寵愛の菊の越度、どのようにお裁きなさいますやら」 「なにっ」 「菊は身寄りのない女。代わって償いをするものもおりますまい。 はて、どうあそばします」 「いや、償いはさせる」 「はて、どのように」 主膳は言葉に詰まった。 最前、お菊が座を外したすきに、皿を隠したのは主膳だった。 自分を嫌うお菊への憎しみから、彼女を困らせるための思いつきであった。 しおらしく詫びてくるならば、許したうえで、日頃の思いを遂げるつもりだった。 そこへ、折悪しくも奥様の出現――。 主膳はのっぴきならなくなった。 寛大に許せば、奥様からは「それみたことか」と罵られよう。 もともと主膳の胸中には、お菊への愛憎が二つ渦巻いている。 いとしさもいとしいが、憎さも憎い。 遊びなれた男なら感情の抑制もきくが、女心に疎いだけに、自分で自分の気持ちを持て余した。 奥様は主膳の出方を見守っている。 お菊は「殿様が自分を困らすためにお皿をお隠しになったのでは…」という疑念が生じていたので、詫びるでもなく黙って頭を下げている。 二人の女にはさまれて、主膳はどうすればいいのかわからなくなった。 ――自分が窮地に追いやられているのも、もとはといえばお菊がすなおに従わなかったのが悪い。 そう思った途端、お菊憎しの気持ちが爆発した。 逆上した主膳は、躍り上がって背後の床の間の刀を取り、 「成敗してくれる!」 抜き打ちにお菊に斬りつけた! ザンッ!! 右腕から肩を切り落とされたお菊は、恐ろしい悲鳴を上げてのけぞった。 血しぶきが音を立てて背後の襖に降りかかった。 奥様はさすがに驚いて夫を留めようとしたが、主膳は狂ったように、二の太刀三の太刀をお菊に浴びせた。 血だるまになったお菊は、畳の上をのたうち回った。血が肺に入ったらしく、ぜいぜいと喘ぎ、畳をかきむしった。 「…あまりといえば、むごいなされよう…。罪なき女を斬り殺して、それですみましょうや。この恨みは…必ず……」 苦しい息の下で言いも終えず、お菊は絶命した。 引き取り手もない一生奴のことである。世間に知れれば面倒とばかり、遺骸はその夜のうちに、裏庭の古井戸に投げ込まれた。 事件の衝撃からか、奥様は予定日より早く産気づき、男の子を産んだ。 青山家にとっては待望の世継ぎで、祝儀の客が引きもきらなかったが、なぜか当家ではさほど喜んでいる様子がなかった。 青山家ではひた隠しにしていたにも拘わらず、世間では奇妙な噂が広まった。 「このたびご誕生の若様は、おからだに欠けたところがおわすそうな」 「それはお菊のたたりに違いない」 そのうちに、 「お菊の幽霊が出るそうな」 と、うわさがうわさを呼び、大きな騒ぎとなった。 お菊の殺された晩から、また梅雨がもどり、じとじとした雨が降り続いた。 そして人も寝静まった深夜になると、お菊の遺骸を沈めた井戸から、ぼうっと光るものが現れた。 やがて、深い井戸の底から、陰気にくぐもった女の声がはいのぼってくる──。 「いちまい、にまい、さんまい……」 声は皿を数える。 「よまい、ごまい、ろくまい……」 哀れにか細い声は、切れるかと思えばつづき、つづくかと思えばふっと消える。 「ななまい、はちまい、きゅうまい」 そこで声がとぎれたかと思う次の瞬間、 「わああぁぁぁ」 引き息に、奈落の底へ引き込まれて行くような恐ろしい叫びが上がり、あとは何事もなかったように、しんと静まり返った。 その声は邸じゅうのものが聞いていた。 主膳は武士らしく強情我慢に何事も起こらぬ風を装い、奥様にも厳しく口止めをしたが、 女中・若党以下の使われている者たちは、そういうわけにはいかなかった。 「もともと罪のないお菊さんを、ああもむごたらしくご成敗あそばすとは」 「絵皿は殿様のお居間で見つかったそうだよ」 「これでは我々も安心してご奉公できないねぇ」 青山主膳の邸は、陰気な空気に包まれた。 せっかく恵まれた初児は、夜も昼も弱々しく泣き通し、とても育つとは思えなかった。 幽霊の声は毎夜続き、臆病な者は恐れて暇をとった。 また、無慈悲な主夫婦に愛想をつかした奉公人は次々に辞めていき、人すくなになっていった。 腸まで腐らせるような霖雨が、静まり返った宏壮な邸を ただ しとどに濡らしていった……。
|
| 後日談―― 噂は公儀にまでも届き、青山主膳は取調べを受けることとなった。 結果、主膳は家内取締り不行き届きということで、所領は召し放され、身柄は親類預け、家は断絶となった。 麹町9丁目にあった常仙寺には、成仏したお菊の納めた絵皿があったそうだが、 いま常仙寺は杉並区の和田本町に移り、その所在は確かでない。 |
