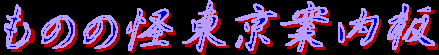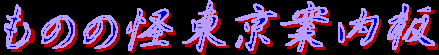|
赤塚松月院
●怪談・乳房榎 ― 赤塚乳房榎と雀の怪 ―
さて、十二社から赤塚へ向かうといっても子連れのことで、新宿へ出たのは九つ過ぎとあってはどこか宿を借りねばならない。
そこでたまたま一泊した宿で、ちょっとした事件があった。
乳がなくてむずがっては泣きやまない真与太郎に、たまたま居合わせた商人風のおかみさんがちょうど張っているからと乳を与えてくれた。そのご主人というのが万屋新兵衛──高田の南蔵院の世話人・原町の新兵衛であった。
何というめぐり合わせか、これも亡き主の引き合わせかと思いつつも、もし真与太郎が生きているとあの浪江に知られては…と考え、正介はここで会ったことは決して他言なさらぬようにと新兵衛に頼み込んだ。新兵衛も正介のそのただならぬ様子に訳ありと察して固く約束をした。
そこから正介は、生まれ故郷の練馬在の赤塚へ向かった。
ここには姪夫婦が住んでいたが、姪とて乳があるわけもなく、正介は真与太郎を抱いては隣村まで乳を貰いに行っていた。
そうしてしばらくは姪夫婦の手伝いに畑仕事などをやっていたが、そうそういつまでも厄介になってはいられぬからと、正介は村の松月院という寺の門番として住み込んだ。
その寺にある榎には、うろのようなところに乳の下がったような瘤が幾つもあり、その先からはまるで乳のような甘い露が垂れていた。
正介が松月院の門番になってまもなくのこと、新宿で出会ったかの小石川原町の万屋新兵衛が松月院を訪れた。
新兵衛の話によると──
──実は、あれから女房の乳に腫れ物ができ、熱を伴って、たいそう痛んだ。しかし医者にかかってもいっこうに治らない。
これは信心するより他はないと、白山様をしきりと信仰した。
するとある夜、夢の中に白山権現が現れ、
「汝、赤塚の榎の下にある我を信仰いたせば、たちまち利益を与える。
その榎から垂れるところの乳を痛み所へつけよ、たちどころに平癒すべし」
とお告げがあった。
新兵衛夫婦は信心肝に銘じ、翌日早速、その赤塚の白山権現を尋ねたのだった。
ところがそれがいっこうにわからず、尋ねあぐねてくたびれて、松月院の門前へ立ち寄ったところに正介がいたのだった。
「それは不思議なこんだが、その白山様の榎っていうのは、おおかたこの門のうちの榎だんべい」
話を聞いた正介は、新兵衛を案内した。
榎の下には額もなければ神号を書いたものも何もない古びたお宮があった。
しかし夢のお告げ通り、榎には乳房のような瘤がいくつもあり、その先からは垂れるほどの露が出ていた。
なるほどこれに間違いないと、新兵衛はその露を竹筒に受けると、正介にいとまを告げて、大急ぎで帰っていった。
正介は、こんな利益のある白山様とは知らなかったので、その日よりさっそく信心して、御膳を上げたりなどしていた。
その後二十一日目に、すっかり病の良くなった女房と新兵衛が二人連れで御礼参りにやってきて、願ほどきに小さな幟と額を納めて、正介にも些少ながらと礼を包んでよこした。
「おまえがここにいたおかげで、尋ねあぐんだ白山様が知れた。
白山様の御利益は覿面で、あれほどに苦しんだできものがたちどころに治ったよ。
これも夢のお告げで、お礼には百人の者へ広めよとのことだ」
新兵衛は松月院へもお経料を納めてその日は帰ったが、さすがに商人だけあって顔が広い、僅か三月ばかりのうちに赤塚の榎はたいそうな評判になった。
その御利益は、乳の病を治すはもとより、乳が出ないのも七日のうちに出るようになる。
そのうちに、人間の乳と少しも違わないで、乳のない子にも榎の乳を飲ませておけば無病でずんずん育つなどという噂がどんどん広まっていった。
参詣者が集まったおかげで、正介は乳を持って帰るための竹筒をこしらえて売るようになり繁盛した。
そして間がな隙がな、この白山権現に
「なにとぞ、主人のせがれ真与太郎を成人させまして、父の敵の磯貝浪江を首尾よく討たせてください」
と、一心に祈り続けた。
そうして月日は経ち、真与太郎も、はや五歳になった。
いたって健やかに育ったものの、田舎の子供そのままで、色は黒く、目ばかり光って、言葉まで在郷言葉。
正介を実の父と慕っては「爺(ちゃん)や爺や」というのを聞いて、正介は情けないことだと涙を浮かべていた。
そんなある夏の末のまだまだ暑い日のこと、いつものように正介が松月院へ参る者に、冷たい井戸の水を盥に汲んで持っていくなどしていると、
「や、おまえは間与島さんの正介どん」
いきなり名前を呼ばれて正介も驚いたが、
「え、なんだえおめえ…ああ、おめえさま竹六さまだな」
「どうも不思議なところで、実にこんな所でおまえに会うとは思わなんだ。
また、どういうわけでここに」
「いえ、このわけは話せば長いこんで、一様や二様のことじゃあねえだが、そうしてまあ、おまえさまがここへ来さっしたのはどういうわけだ」
「いや、これにはいろいろわけありで」
竹六は今も柳島の屋敷に出入りして、あれこれ用事を言い付かっていた。
「もう足かけ五年前になるね。
先生が落合で殺され、浪江さまが跡へお直りなすって、そこまではおまえも知ってだっけ。あれから御新造がお産があってね、お生まれなすったのは男のお子で。
ところが御新造も、真与太郎さんを連れておまえが行き方知れずになったとお聞きなすって、心を痛めたもんだから、お乳が少しも、相変わらずさ、出ない。
さあ旦那が気をもんで、あるとあらゆるお医者にかかったが出ない。
その中に赤さんは乳がないからやせ衰えて、とうとうおかわいそうに、亡くなった。
その取り片づけをしてちょうど七日目のことだ。
御新造の乳の上のところへおできがぼっつりとできたが、その痛むこと恐ろしい。
昼夜、御新造はころころ転がって、ヒイヒイと痛がっておいでなさる。
聞けばこのごろ赤塚の乳房榎の白山様へ願をかければ乳いっさいの病ならじきに治ると評判で、とうとう竹六そのお役に当たって、早く行ってそのお乳とかを頂いて来てくれと、まあ言われてやってきたわけだ。
で、それはそうと、おまえはまたどうして柳島を出なすったのだね」
「竹六さん、これにはだんだんわけのうあるこんだが、おれ先の旦那にゃあ大恩受けたから、その恩返しをするつもりで坊ちゃまを連れて走っただよ。
ありがてえこんに、おれ一心届いて丹精してようようのこんで成人させただ」
「え、それでは、坊様は今でもお達者で」
「ええ、ことしで五つだあよ。
これ、真与太郎さん、ここへ来て、竹六じいやァにお辞儀をするだあよ」
と、傍らの坊を呼び寄せた。
「おらあ、お辞儀なんてこと知んねえよ」
「知んねえじゃあねえ、困ったよ。
竹六さん、見てくだせい、これが坊ちゃまで」
「え、この色の黒い餓鬼が……いえなに…このお子がかえ」
竹六は驚いて、しばらく真与太郎の顔を見つめて、
「おお、坊さまかえ、たいそうりっぱにおなんなすった。
どこかお父さんに面差しが似ておいでのはうれしい」
「おいらァ爺(ちゃん)はここにいるのが爺だ。他にお父さんはねえ」
「ねえとおっしゃっても、争われないよ、口もとが先生に似ておいでだ。
もし、坊ちゃま」
「おれ坊ちゃんて名じゃあねえよ。馬鹿やい」
と竹っ切れを振り回して、真与太郎は田んぼの方へ逃げていってしまった。
「どうもさっぱりしておいででいい。
だが正介さん、ここにおいでのはどういうわけで」
「俺が身の上を話せばやっぱり長えだ。実は……」
正介は虚実を交えて、これまでの経緯を話した。
「そうかえ、それでおまえが男手一つで…なかなかそれはできない。
お亡くなりなすった旦那がさぞ草葉の陰でお喜びだろう。
感心だ、恐れ入った。竹六感服……」
「おめえさま、今話したこと包まずにいうのだから、もし浪江さまが聞くと癇癪持ちだから、あの爺め、ふてえやつだ、と斬りかねねえ。
どうかここでわしに会ったことは、いっさい他言してくれるな」
「なに、そんなことは案じねえがいい」
竹六はそう約束して、涙賃と称して些少の金子を正介に手渡した。
榎の乳を貰い受けた竹六は、まっすぐ柳島へと飛び帰った。
「へい、竹六ただいま帰りました」
奥では、日暮れからまた痛みがぶり返したらしい、おきせがうんうんと唸って苦しんでいた。
竹六の帰りを待ちかねていた浪江は、さっそく
「おお、御苦労御苦労。乳は貰ってきておくれかえ」
「へい、これでございます。この竹筒のほうへ入れてまいりました。
御新造さま、早く召し上がれ、直にお治りで不思議だそうでございます。
へい、ずいぶん大きな榎で、その前に棚が吊ってありまして、その上に治った人がお礼に上げたという、竹づっぽうへ入れた乳が名前が書いて上がっておりまして。
その竹づっぽうや土器やらはじき門の脇の茶屋で売っておりまして、そこにあなた、あの正介が……いえ、なに、正、正直そうなおやじが…」
とつい口走った竹六はなんとかごまかしたものの、日頃から心に掛かる正介のことだけに浪江は聞き逃さなかった。
「今おまえ、正と言いかけたが、もしや正介がそこにおって会いでもいたしたか」
「え、なに正介殿に、なに会いはしません。
さあ御新造、お乳を上がれ、直に験が見えます。
わたくしがそれに一生懸命にお願い申してきましたから、御願が聞きますことは竹六お請け合い、その代わりにすっぱりよくおなんなすってお礼参りというときには、わたくしは是非御案内かたがたお供でござりましょうね。
ええ、では旦那さまお大事に。また明日。お休み遊ばせ」
竹六は話をはぐらかして、これ以上詮索されないうちにとあわてて帰った。
おきせの乳の上のでき物は、中に埋もれたまま真っ赤に腫れ上がっていた。
貰ってきた榎の乳を絵筆に付けて腫物に塗ると、その御利益か、おきせは何日かぶりにぐっすりと眠った。夜伽の下女たちも安心して、その夜は皆そろって眠ってしまった。
明け方近くになって、また痛みのひどくなったおきせは傍らの浪江を揺り起こし、
「あなた、ちょっとお起きあそばしてください…
もし、まことに痛んでなりません……あなた」
「また痛んでまいったか」
「はい、宵の口はあの乳をつけたせいでしたか痛みが薄らぎましたが、もう怖い恐ろしい夢を見ましてから、またたいそう痛んで…」
おきせはびっしょりと汗をかいていた。が、下女を呼んで着替えをさせようとする浪江を引き留めて、
「あなた、幸い誰もそばにおりませんから、ただいま見た夢を」
「なんだえ、夢とな。いけんよ、夢なんぞを気にしてはかえって病に障る」
「いえいえ、気にかけずにはおられません。
枕元へ先の夫・重信が、血塗れで、それはもう恐ろしい顔をして、わたくしを恨めしそうに睨めまして――
それはもう…もう何とも申せぬ顔をいたして、わたくしの髻をとって引き倒し、『この犬畜生め、よくもおれを落合の堤で殺したな、汝にも思い入れ苦痛をさせねばならん』と言って打ち据えます。その恐ろしいこと…恐ろしいこと……
…あなた、わたくしがこんなに苦しみますのも、五年前に夫が留守中にあなたと深い仲になりまもなく落合とやらで非業な死を遂げ、まだ百ヵ日も済まないうちに、あなたと夫婦になった罰でございましょう。
とろとろといたしますと、夫の姿が目に焼きついて……ああ痛っ!
雀が…できものの中に雀がおります…
あれあれ、雀がたいそう来ました。雀ができものを突っついて…あれあああ」
「これ、雀がどこへまいった。雀がなんでまいるものか。馬鹿を言ってはいかん。
そんなうわごとを言うのは熱の強いせいだ。
雀などではない。できものが疼いておるのだ」
「いえいえ熱のせいではございません。
本当に雀がチュウチュウ申して…雀が…雀がお腹の臓腑を突っつきます……
ああ… あなた、ちょっと見て下さい」
おきせの乳の下のできものは、三寸ほどの大きさまでに、まるで硝子玉のように腫れ上がっていた。
「これは痛そうだ。これは中がまるで腐っておるのだろう。
いっそ膿を出したら痛みが去るかも知れん」
「わたくしもそう存じます。
どうぞあなた、小刀かなにかで突っついて下さいまし」
「そんな荒療治はできん。医者のまいるまでもう少しの辛抱じゃ」
「いえ、この通りブクブクいっておりますから、切ればすぐに膿が出て痛みが去りましょう。
あなた、早く…早く…」
せきたてられて浪江は、
「よい、それでは切ってやろう。少しは痛かろうが我慢いたせよ」
と枕元の小柄で、できものを突こうとした。が、どういう手先の狂いであろうか、左胸へ五、六寸も深く切り込んでしまった。
血交じりの膿が疵口からほとばしり、それといっしょに白緑色の異形な鳥が現れた。
浪江があっけに取られて呆然としているうちに、小さな雀ぐらいの鳥は、たちまち鳶ほどになり、浪江の頭をめがけ、鋭いくちばしで襲いかかった。
「畜生、畜生…」
浪江はそこらにあった棕櫚箒で追い散らそうとするが、異形の鳥はふわりふわりと風のように舞い、まるで手応えがない。
騒ぎに目を覚ました看病人や下女が駆けつけたときには、おきせは既に絶命しており、浪江は箒を持ったまま疲れ切って倒れていた。
異形の鳥は姿形もなく、なおも不思議なことには、おきせの胸の傷からは膿が出ているだけで、ほとばしった血の痕はどこにもなかった。ただ、反り返って歯を食いしばったときに舌を噛み切ったらしく、口から血を流して死んでいた。
それからおきせの弔いを早々に済ませた浪江は、竹六を嚇して赤塚の正介の居場所を白状させて、その足で赤塚へ向かったのが七月十二日のことだった。
一方その頃、赤塚の正介はお迎い火を焚いて、重信の位牌を持って、真与太郎に真実を打ち明けていた。
「坊ちゃま、よく聞かっしゃいよ。
おめえさまの父さまは浪人こそなすったが、元は二百五十石取ったりっぱなお侍だ。
器量よしの御新造持ったのが身を滅ぼす瑞相で、磯貝浪江という悪人のために殺されただ」
そう言うと、正介は錆びた刀を取り出して、
「この刀ァな、おめえさまを角筈の十二社の滝壷へぶち込めって言われて出てきたとき、犬脅しに差してきたなまくらで、こんなに錆びているだが、こっちが一生懸命ならこれだって恨みは返せる。
おれが助太刀するから親の仇を、ええか、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」
麻幹をくべて念仏を唱えていると、かの磯貝浪江が押しかけてきた。
正介は驚いて逃げようとするも、一方口で逃げ場がない。
浪江は上がり框に片足踏みかけ、居合腰に体を縮めて刀をすらりと抜き、
「珍しや正介、この浪江を仇とねらうなどとは片腹痛し。
いで小児もろとも真っ二つにいたしくれん!」
と、刀を真っ向に振り上げた。ところが葺き下ろしの茅葺き屋根で内法が低いから、切っ先が鴨居へがっちりと食い込んだ。
逃げ場を失った正介は仏壇にあった瀬戸物の香炉を取って浪江にぶつけ、灰は四散して浪江の両眼にはいった。正介はここぞと思い、有り合わせた樫の木の心張り棒で腰の辺りへ三つ四つ食らわし、「坊ちゃま、そら仇だ」と振り返ったところ――
真与太郎の後ろで手を持ち添える影が、灰神楽の中でぼんやりと浮かび上がった。
「おとっさんの仇、思い知れ」
と高らかに呼ばわり、真与太郎は錆刀で浪江の横っ腹へ突きこんだ。
その後、正介真与太郎は名主預けになり、法の如くお咎めを受けたが、正介はのちに髪を剃って回国の出て亡き人々の回向をし、真与太郎は五歳で親の仇を討ったのは珍しいと、旧主秋元家へ十五歳になったら帰参させよと御奉書を賜わり、それまで遠縁の者に引き取られたという――。
|