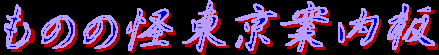
|
本郷本丸本妙寺/本所回向院
●振袖火事
その年、明暦3年(1657)は、新年早々からしきりに火事が起こっていた。
元旦には四谷竹町から出火、4日5日にも続けて火事騒ぎがあった。 冬の江戸は雨量が少なく、空っ風が吹くのは例年のことだが、前年の11月からこの年にかけてはことに異常気象で、一滴の雨も降らなかった。 乾ききった空気は、ちょっとした不始末からたちまち火事をよんだ。 「いやな風が吹くねぇ」 正月18日は朝から、乾(北西)の強い風が吹き荒れ、戸障子を揺さぶり、道の土埃を舞わせた。 江戸庶民は寒さに肩をすくめながら、不安げに囁き交わした。 昼少し過ぎに、本郷本丸の本妙寺の門前にはちょっとした人だかりができた。 本堂では読経が始まっていた。 「噂どおり、お供養をするのかい」 「振袖を焼くたぁ、珍しいじゃねぇか」 「何とももったいない話だね」 「けど、おめえ。とんでもねぇ因縁つきの振袖だってぇじゃねぇか。 いっそ焼いちまうのがいいのさ」 「若い娘が三人も……だってぇからね」 「くわばら、くわばら」 人々は、そそけ立った顔を見合わせた。 それは、2年前の話に始まる──。 明暦元年(1655)、日も同じ1月18日、この本妙寺へ布施として一枚の振袖が納められた。 紫縮緬の大振袖に、荒磯と菊を染め出し、桔梗の縫紋を付けた目のさめるように華やかな柄行であった。 この振袖を身にまとったのは、むろん年若い娘で、名は梅野。麻布百姓町で質店を営む遠州屋彦左衛門の一人娘であった。 承応3年(1654)の春、梅野は母に付き添われて上野の山へ花見に出かけた。 当時、花見は芝居見物とともに、女の大きな楽しみの一つであった。 江戸時代の中流以上の家庭の婦女子というのは、今考えるよりはるかに、外出の機会が少なかった。他国への旅行など、女は滅多にできなかったし、買い物に出歩くということさえまずなかった。いったん、外出するとなると、娘ならば母親か乳母、上女中が付き添い、妻女には女中などの供がつく。町内の稽古所や銭湯を除けば、一人歩きなどというものは殆どなかった。 いったん、外出するとなると、娘ならば母親か乳母、上女中が付き添い、妻女には女中などの供がつく。 町内の稽古所や銭湯を除けば、一人歩きなどというものは殆どなかった。 それだけに、年に数えるほどの物見遊山は、心躍る楽しい出来事であった。 梅野も早くから花見振袖を新調し、その日がくるのを指折り数えて待っていた。 遠州屋も大切な一人娘を今日を晴れと着飾らせ、母、乳母、女中のほか、店の若い衆に提重などを持たせ、小袖幕の用意などして賑々しくくりこんだ。 母をはじめ、女中や店の者に取り巻かれ、美しく装った梅野は、花の間を逍遙しながら野に放たれた小鳥のように、うきうきと心が弾んだ。 艶やかな頬は上気し、興奮から目は輝いていた。通りすがりに同年輩の娘の衣装に素早く目を走らせては自分の衣装と比べて、品定めするのも忘れない。 その時、前方から、目を奪うように派手やかな衣装を着た者が近づいてきた。 女ではなく、前髪立の寺小姓であった。 ──なんと見事な。 相手の衣装を見、ついで顔を見て、梅野は息を呑んだ。 雪をあざむく白い額に、前髪がはらりとふりかかって、彫り込んだようにくっきりした目鼻立ちといい、これまでに見たこともない美少年であった。 当時、不邪淫戒を守る僧侶は、競って美しい寺小姓を置いて寵愛したが、わけても上野寛永寺の寺小姓は、粒選りと定評があった。 あっと思う間に少年は人混みに紛れてしまった。 が、その面影は梅野の胸に焼き付いて離れなかった。 2、3日して、梅野は母に新しい振袖がほしいとねだった。紫縮緬に荒磯と菊を染めるようにと、色や柄についても細かく注文した。 母は言うなりに、染物屋へあつらえてくれた。 振袖が仕立て上がってきた日、梅野は人目のないところで、その衣装をひしと胸に抱いた。 梅野はその振袖に手を通そうとしなかった。 その代わり、枕に着せて、生きている人に語るように問答した。 ──いじらしくも、梅野は最初から恋をあきらめていた。 「まあ、十五にもなって、まだ人形遊びかえ」 母も乳母も笑ってみていたが、そのうちに様子がおかしいと気付きだした。 梅野は始終、軽い熱を出し、弱々しい咳をするようになっていた。 俗に言う“恋煩い”である。 梅野が片思いに悩んでいると知って、両親は当惑した。 しかし、日に日に弱ってゆく娘を見るに耐えかねて、上野あたりの寺小姓らしいというのを手がかりに、懸命に探し回った。 だが、いっこうにそれらしい少年の所在はつかめなかった。 ──掴めなかったのではなく、娘に“不しだら”の汚名のつくことを恐れて、あえて少年と会わせなかったに違いない。 花見の日には母親も乳母も同行していた。恋に患うほどの娘の変化を見過ごすとは思えない。とうの昔に少年の顔は知れていたろうが、わからぬふりを続けていたのだろう。 そのうちに、娘も諦めるに違いないと践んでいたことだろう。 しかし、梅野はしだいにやせ衰えて、翌年の正月、あの振袖をしっかり抱きしめたまま、露のように儚く亡くなった。 嘆き悲しんだ両親は、娘の思いの残る振袖を菩提寺の本妙寺に納め、冥福を祈ることにした。 さて、寺としては、華美な振袖を手元に置いてもしかたない為、出入りの古着屋へ売り渡された。 そして、その一年後の正月十六日、振袖は再び本妙寺へ荷われて来た。 棺の主は「おきの」といい、上野山下で紙を商う大松屋又蔵の娘であった。 葬儀のあと、大松屋は、「娘のたいそう大切にしておりました振袖でございます。なにとぞ、こちらへお納めを」と申し出た。 本妙寺では、だまって振袖を受け取った。 そしてまた翌年の正月、三度、あの振袖を目にして、寺のものは目を見合わせた。 この度は本郷元町に住む麹商い喜右衛門の娘「おいく」の棺に掛けられていた。 梅野の妄執が残って、他の娘たちに祟りをなすのであろう。 江戸人たちは、因縁の絡まる振袖の噂でもちきりだった。 男も女も怖いもの見たさから、振袖供養の当日、本妙寺へ集まった。 未の刻(午後2時ごろ)、さかんな施餓鬼の行われ、僧たちが庭火を囲んで声高く経を誦する間に、振袖が火中に投じられた。 燃えさかる炎はたちまち紫の振袖を包むかに見えた。と、そのとき一陣の突風が巻き起こり、あっという間もなく振袖を引っさらった。 目に見えぬ強い力に引かれるように、虚空高く舞い上がり、下から見上げる人々の目にそれは、人の立ち上がって手を広げた姿そのままに見えた――。 一面に火のついた振袖は、八十尺といわれる本堂の屋根に引っかかった。 火の粉が雨のように降り注ぎ、人々が大騒ぎする間に、本堂の棟木に燃え移った。 こうして本堂から出た火は、その日のうちに江戸八百八町の大半を焼き尽くしたのだった――。 |
|
|
|
「振袖火事」と呼ばれる明暦の大火の死者は十万八千余。 当時の江戸の人口は三十五万余であったことからも、 関東大震災や第二次世界大戦にも等しい大きな災害であったのがうかがえる。 火は一晩で、湯島、神田辺、浅草御門内町屋、通町筋、鎌倉河岸、京橋八丁堀、霊岸島、 鉄砲洲、海手、佃島、深川までをなめ尽くし、江戸城本丸、天守閣もこのとき炎上した。 いったんは収まった火事であったが、翌日の19日巳の刻(午前10時)過ぎ、小石川伝通院前新鷹匠町から再び燃え出し、 牛込御門、田安御門、神田橋御門、常盤橋御門、呉服橋御門、八代洲河岸、大名小路、数寄屋橋御門前を焼き払った。 また同日、番町から出た火は、半蔵御門外、桜田虎御門、愛宕下、増上寺門前札の辻、海手までを焼いた。 羅災したものは、万石以上の大名屋敷が500余、旗本屋敷が770余、神社仏閣350余、町屋400町、片町800町との記録が残っている。 このあまりにも多くの焼死者を葬るために、本所回向院は作られた。 この大火を境に、江戸の様子は大きく変わった。 日除地をつくり、道を広げて広小路にし、両国橋を作った。 定火消しの制度もこの翌年に誕生している。 定火消し、方角火消しなどというのは、武家の率いる火消しで、大名自身が馬上姿で颯爽と陣頭指揮をとったりした。 町火消しができるのは、もっと後年のこととなる。 |
|
|
|
さて、これを陰陽五行に当てはめると、興味深い内容が浮かび上がる。 まず、梅野が恋に燃えた1654年は午年。火気のもっとも盛んな年である。 そして、亡くなった翌年は未年。火気ばらみの土気の年である。 これは、土気の中でも最も強い力を持っているとされる。 これは私の見解にすぎないが、火気に生み出された恋は、翌年の妖気を孕んだ火気によって、あやかしの念を持ってしまう。 さらに、これに木気が関わる。 出会いは春。亡くなった日と火事の起こったのが1月。どちらも木気である。 『木生火』で、木は火のパワーを増幅させる。 また、梅野の振袖は『紫縮緬』。木気の青と火気の赤を合わせた色である。 それが、翌々年の1657年、酉の年に災いをもたらした。この年は金気の中気である。 『火剋金』── 金の年は木の力を得た火の妖気に剋されたと解釈できなくもない。 さらに出火の始まりが未の刻、一時収まった火が再び燃え上がったのが巳の刻、 ともに火気の時刻であったことも見逃せない事実である。 |
